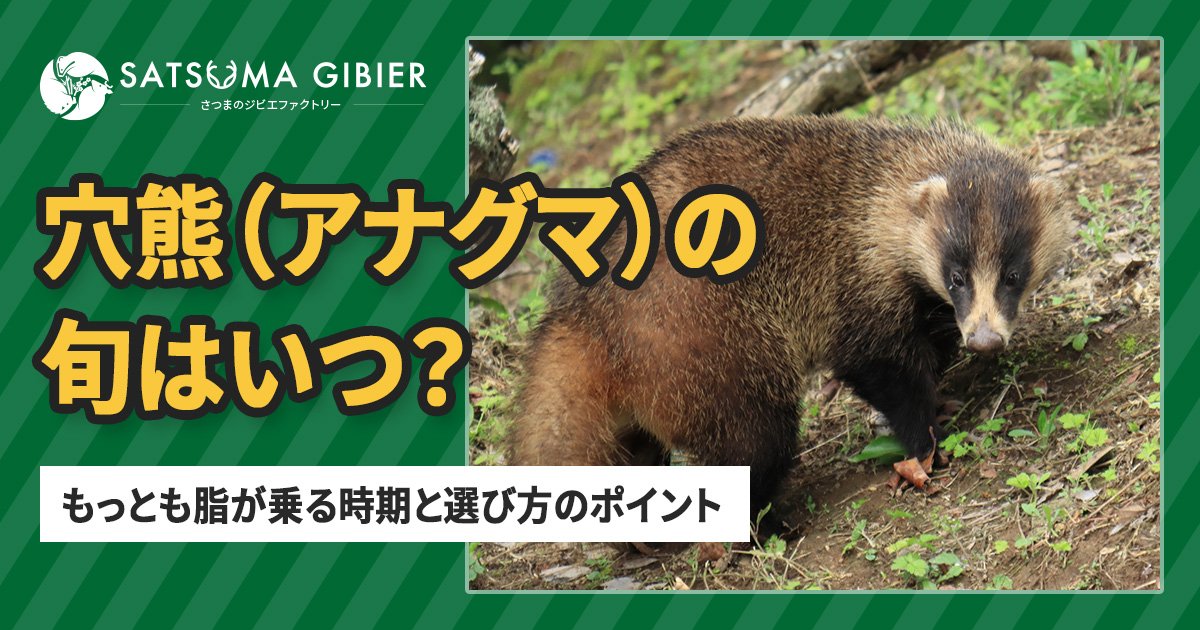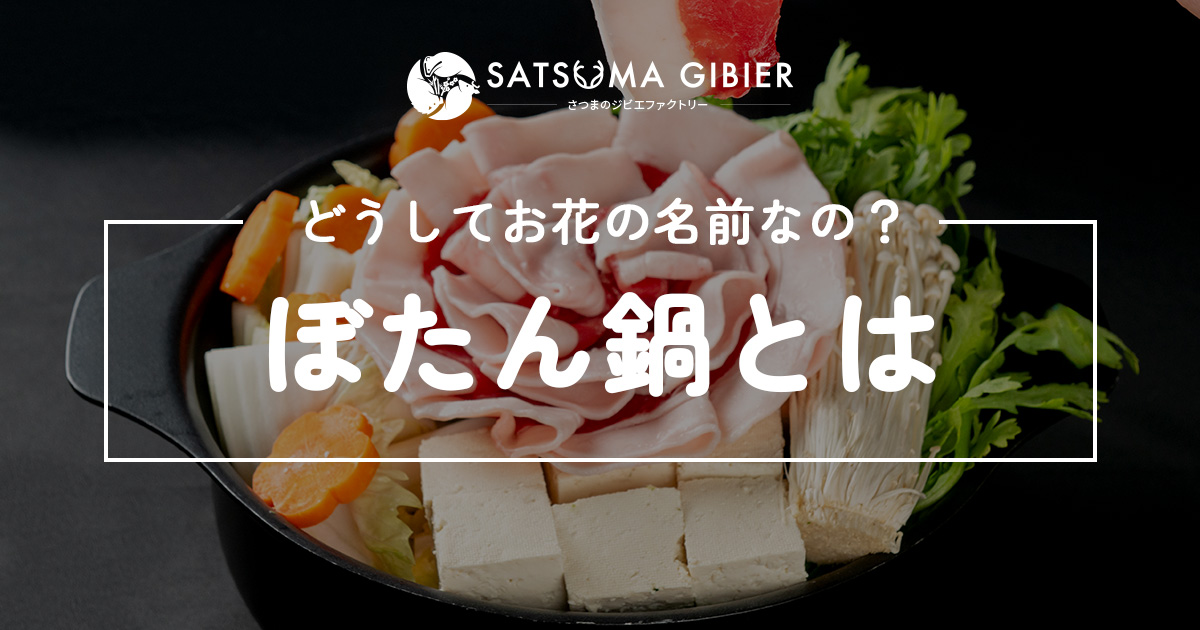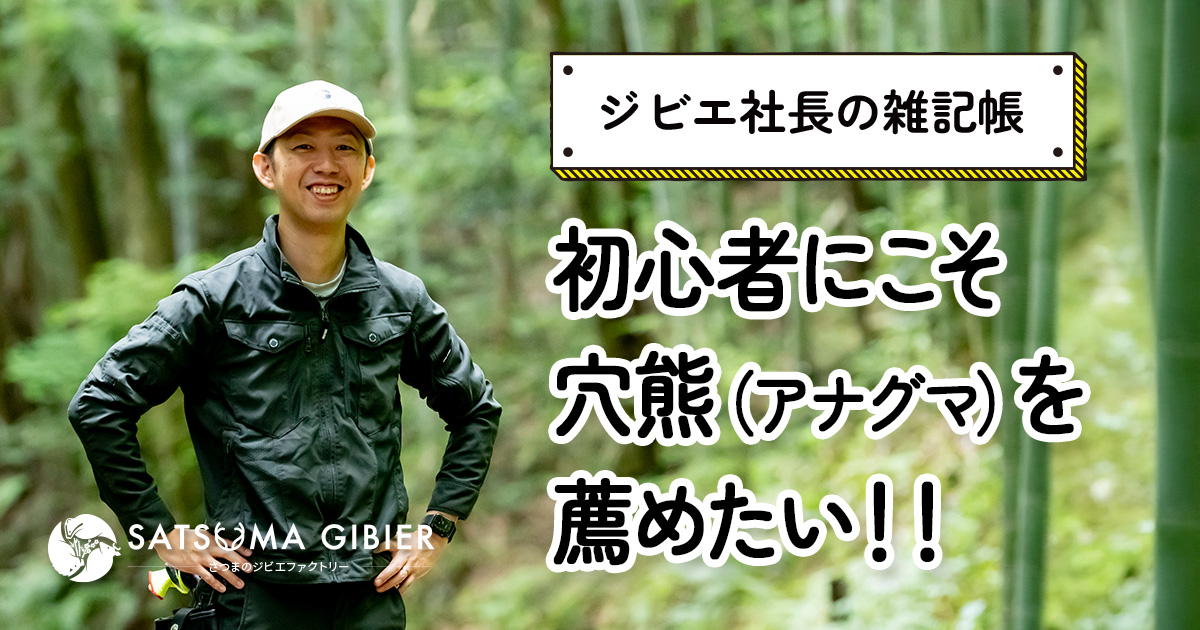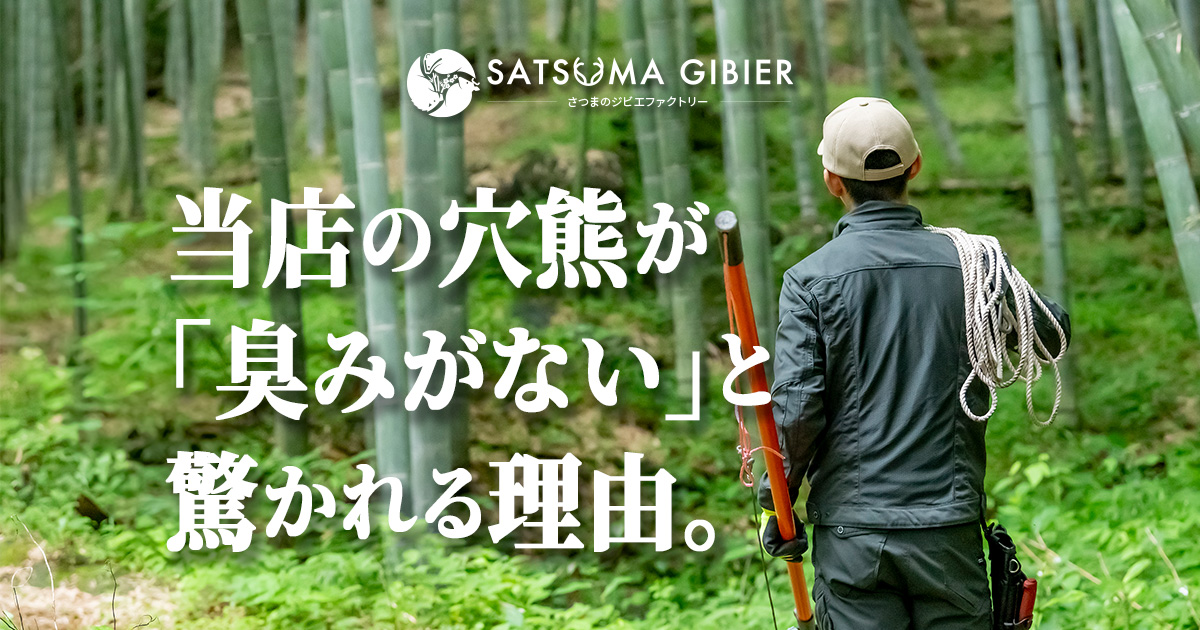はじめに
近年、ジビエに対する関心が高まり、飲食店などで提供される機会も増加しています。ジビエとは、シカやイノシシなどの野生鳥獣の食肉を指し、高タンパク質・低脂肪で栄養価が高い食材として注目されています。しかし、野生鳥獣を食肉として利用するためには、安全性確保の観点から、捕獲から流通・消費に至るまでの適切な管理が不可欠です。
この記事では、ジビエ食の安全を守る上で重要な要素である「捕獲ルール」と「トレーサビリティ」について解説し、消費者が安心してジビエを享受できる環境づくりの必要性について
捕獲ルールの重要性

ジビエの安全性を確保するためには、捕獲段階における適切な管理が重要となります。具体的には、以下の点に留意する必要があります。
2.1 適正な狩猟方法の確立
- ・法律に基づいた狩猟(狩猟免許・許可制): 狩猟は、鳥獣保護管理法に基づき、狩猟免許の取得と都道府県知事による狩猟許可が必要となります。狩猟者は、法律や倫理を遵守し、適正な狩猟技術を習得することで、安全なジビエの捕獲に貢献します。
- ・適正な狩猟時期(猟期の設定): 狩猟可能な期間は、鳥獣の種類や地域によって定められています。これは、鳥獣の繁殖期や生態系への影響を考慮し、持続可能な利用を図るためです。
- ・生息数管理と持続可能な利用: 鳥獣の生息数は、地域や環境によって変動するため、適切な管理が必要です。過度な捕獲は、生態系のバランスを崩す可能性があるため、科学的なデータに基づいた生息数管理と持続可能な利用が求められます。
2.2 衛生的な処理方法
捕獲後の処理方法も、ジビエの安全性に大きく影響します。
・二次汚染の防止: 処理過程において、土壌や糞便などによる二次汚染を防ぐため、清潔な環境を整備し、衛生的な作業手順を遵守することが重要です。
・捕獲後の迅速な内臓除去: 捕獲後は、できるだけ早く内臓を除去することで、腐敗や細菌の増殖を抑制し、食肉の衛生状態を保ちます。
・血抜きや冷却の適切な管理: 血抜きを十分に行い、適切な温度で冷却することで、肉の品質劣化を防ぎ、安全性を高めます。
2.3 有害物質のリスク管理
・寄生虫や感染症対策(E型肝炎ウイルス、トキソプラズマなど): 野生鳥獣は、E型肝炎ウイルスやトキソプラズマなどの寄生虫や病原体を保有している可能性があります。これらの感染リスクを抑制するため、適切な検査や加熱処理が必要です。
・鉛弾の使用制限(鉛中毒の危険性): 鉛弾を使用した場合、鉛が食肉に残留し、人体に悪影響を及ぼす可能性があります。鉛中毒のリスクを低減するため、鉛弾の使用を制限し、代替となる弾丸の利用を促進する必要があります。
トレーサビリティの重要性

トレーサビリティとは、食品の生産・加工・流通の過程を記録し、追跡できる仕組みのことです。ジビエにおいても、トレーサビリティは安全性を確保し、消費者の信頼を得る上で重要な役割を果たします。
3.1 ジビエの安全性を保証する仕組み
- ・捕獲地・捕獲者の記録: 捕獲された場所、日時、捕獲者などを記録することで、ジビエの由来を明確化し、問題発生時の迅速な対応を可能にします。
- ・衛生処理施設での検査・管理: 衛生処理施設では、食肉の検査や処理が行われます。獣医師による検査や衛生的な処理工程を記録することで、食肉の安全性を確保します。
- ・食肉加工から流通までの追跡システム: 食肉加工、包装、流通の各段階における情報も記録・管理することで、流通経路を明確化し、問題発生時の原因究明を容易にします。
3.2 消費者の安心と信頼を得るための情報開示
・スマートタグやQRコード活用で詳細情報提供: スマートタグやQRコードを活用することで、消費者は、スマートフォンなどから捕獲場所や処理方法などの詳細情報にアクセスできるようになり、ジビエへの理解を深めることができます。
・ラベル表示の義務化(産地、処理日、衛生検査結果など): ジビエのラベルには、産地、処理日、衛生検査結果などの情報を表示することで、消費者がジビエの安全性を確認できるようになり、安心して購入することができます。
具体的な安全管理の取り組み
ジビエの安全管理は、行政、自治体、民間団体、生産者など、様々な主体が連携して取り組む必要があります。
4.1 行政や自治体のガイドライン・基準
- ・厚生労働省の「ジビエ衛生管理指針」: 厚生労働省は、「ジビエ衛生管理指針」を策定し、ジビエの衛生管理に関する基準を設けています。この指針は、捕獲から食肉処理、流通、販売に至るまでの各段階における衛生管理の基準を示し、安全なジビエの提供を促進するためのものです。
- ・各自治体のジビエ認証制度: 各自治体では、独自のジビエ認証制度を設け、地域におけるジビエの安全管理を強化しています。認証制度は、地域ブランドの確立にも繋がり、消費者の信頼獲得に貢献します。
4.2 民間団体・生産者の自主的取り組み
・地域ブランド化による品質向上: 地域独自のブランドを確立することで、ジビエの品質向上や安全管理の強化を図り、消費者の信頼獲得につなげることができます。
・HACCP(危害分析重要管理点)導入: HACCPは、食品の製造工程における危害を分析し、重要管理点を特定することで、安全性を確保するための衛生管理手法です。HACCPを導入することで、ジビエの生産・加工における衛生管理レベルの向上を図ることができます。
・GPSやデジタル管理でトレーサビリティ強化: GPSやデジタル技術を活用することで、捕獲場所や捕獲日時、処理工程などの情報をより詳細に記録・管理することが可能となり、トレーサビリティの強化につながります。
まとめ・今後の課題
ジビエ食の安全を守るためには、捕獲ルールとトレーサビリティの両面からの取り組みが重要です。関係機関や事業者は、連携を強化し、衛生管理の徹底、情報公開の推進、地域ブランドの育成などに取り組む必要があります。
消費者は、ジビエの安全性に関する情報を積極的に収集し、信頼できる販売業者から購入することが大切です。
ジビエは、地域資源の活用、食文化の振興、鳥獣被害の軽減など、様々な効果が期待される食材です。安全管理を徹底することで、ジビエの普及を促進し、持続可能な社会の実現に貢献していくことが期待されます。